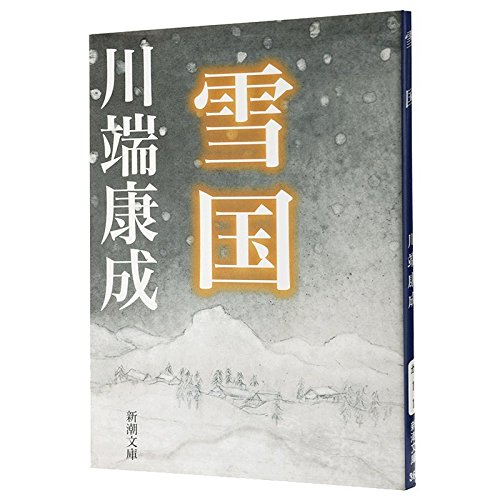【感想】川端康成の『雪国』は不倫だけど純愛だと思った
『雪国』は、「あ、なんか、すごくイチャイチャしてんなー」というのが読んだ感想だった。
なにも、えっちな描写がすごいとか、浮かれているとか、夢や希望であふれているとか、そういうイチャイチャじゃない。(むしろ、えっちな描写は川端康成に天才的な文体によって美しく省略されている。)
名作である『雪国』に対する感想としては不適切なのかもしれないけど、主人公である島村と駒子がイチャイチャしている様子を見て、照れてしまうような気持ちになった。
お互いに「好きだから会いに来た」という一点のみが強調され、これからの二人の未来がどうだとか、過去がどうだったかとか関係ない。「できる限り長く一緒に過ごしたい」という「今」を切り取った物語だからなのかな、と思った。
作家・川端康成
『雪国』は、川端康成の著作。
川端康成は1899年生まれ。出身は大阪府。
1968年にノーベル文学賞を受賞している。
1972年に亡くなっているが、死因は自殺とされているが、事故死説もあり。
あらすじ
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」というか有名な書き出しで始まる物語。
ちなみに、その次に続く文は「夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。」である。
主人子である島村は、親譲りの財産で生活しているため定職についていない。ふらふらとやりたいことをやって生活していて、趣味が高じた小遣い稼ぎをする程度。特に人生において目標や生きがいはなく、世捨て人のような生活をしている。けど、妻子あり。
島村は、妻子がありながら芸者の駒子と恋仲となる。といっても、愛人として囲っているとか、定期的に逢瀬を重ねているとか、そういう関係じゃなく、島村の気が向いたときにふらっと駒子の働く温泉町に会いに行くような、いわばゆきずりの関係。
そんな二人の関係性のもと、冒頭の書き出しは島村が駒子のいる温泉町に向かうシーンであり、島村がそこに長逗留して、駒子が島村の泊まる部屋に足しげく会いにくる、という話。
不倫だけど純愛
島村は、妻子がありながら駒子と関係を重ねていく。
はっきり言って不倫だけど、作中では妻子への負い目とか、葛藤とか、まったく描写がない。
たぶん、妻子のことを本当は気にかけているけど描写がないだけ、ではなくて、本気で島村は不倫についてまったく問題にしていないと思う。
それはきっと、島村が親譲りの財産で生活していて、労働という生活に根ざした苦役を負っていないから。それゆえに、生活感のない現実離れした価値観をもってしまっているから。
自分についても、他人についても、「生きる」という行為についての実感が希薄なんじゃないかなと思う。だから、自分の感情も、他人の感情も、あまり本気になって大事にしない。
普通なら、駒子に対しても申し訳なさを感じると思う。
芸者で身を立てる駒子の生活を楽にしてあげたいなとか、精神的な支えになってあげたいな、とか。
でも、島村はそんなこと考えない。
「僕はなんにもしてやれないんだよ。」とか言っちゃう。
いっそ、冷たいとさえ思える。
そんな島村との関係だから、駒子との恋愛には「過去」も「未来」も入りこむ余地がない。
徹底的に「今」の瞬間だけの関係。
少年少女の恋愛のように、「今、会いたいから会いにきた」というのが切実に浮かび上がる。
そういう意味で、不倫だけど純愛と言えるんじゃないかな。
最高にイチャイチャしてんなーって思った。
省略の美しさ
よく、『雪国』は省略が美しいと言われる。
例えば、夜に駒子が島村に会いに来たと思ったら、次の一文では朝のシーンに切り替わっていたりする。それで、お湯に入ってくるねーとか会話している描写を読んで、「朝まで一緒にいたんだな。これはえっちなことをしたな」って想像する。
そういう行間で読ませてくる文体だから、読み慣れないとわかりにくいと思うんじゃないかと思う。
それでも、文章自体(使われている言葉とか、言い回し)はわかりやすくて、ほかの文豪と呼ばれる人たちの作品よりは各段に読みやすい。
実はこの作品は二度読んだ。学生のときと、社会人になった今。
学生の頃に読んだときはまったく面白いと思わなかったけど、社会人になって読み直してみると面白い、さすが名作だな、と思った。